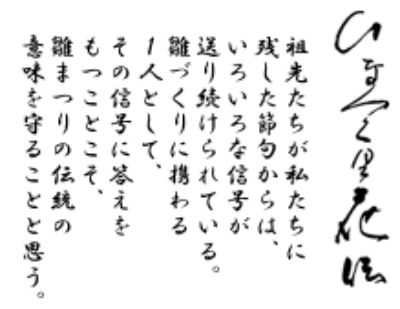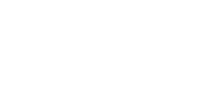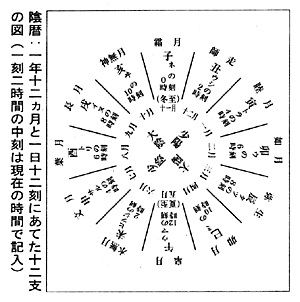
(1)赤い糸で結ばれている私のおひなさま
十月は陰暦では和名を神無月とよび、十二支で数えると亥(い)(猪)の月とよんだ。
国中の神々は出雲の国に集まり、出雲以外の各地の神様の社(やしろ)は、神不在の月にあたる。それゆえ、神前での婚礼は無意味なものではと思えるのに、十月は婚礼のシーズンとされ、婚礼の知らせもこの月に重なりやすい。なぜなのか。そこには神無月の神不在を俗説として寄せつけぬほどの何かがあるのだろうか、興味をそそられる。
そのことはさておき、婚礼の歴史を知るうえで、面白い記述がある。
「婚礼は夜する物也。されば古法婚礼の時、門外にてかゞり火をたく事、上臈(じょうろう)脂燭(しそく)をとぼして迎に出る事旧記にある也。男は陽也、女は陰也。昼は陽也、夜は陰也。女を迎うる祝儀なる故、夜を用ル也。唐にても婚礼は夜也。されば婚の字は女へんに昏の字を書也。昏はくらしとよみて日ぐれの事也。今大名などの婚礼専ら午の中刻などを用る事、古法にそむきたる事也」。
江戸期の『貞丈雑記』にある考峯で、祖先たちが婚礼にどう臨んでいたのかが分かる。ここで大切なことは、自然界の時の流れであろう。陰と陽の二元に対する思い入れである。
一日に昼と夜の陰陽があるように、四季一年にも陰の季節と陽の季節の循環があり、その区分がなされる。
月日や時刻まで十二支の数詞でよんだ昔、十月は亥(い)(猪)の月にあたる。陰暦での十月は、冬至がまわってくる子(ね)(鼠)の月を前に、一年では一番日脚が短く、夜長の時期。夜の陰の深まりが四季を通じて最も強く感じられる月であり、十二支最後の亥の月になっている。
冬至を境にして日脚は少しずつ伸びる。陰極まれば陽に転ずるたとえの通りに、亥の月には冬至を前にして一陽来福という明るい伸展への願いがあったに違いない。冬の寒さを表したものに、「冬至、冬なか、冬はじめ」という気象用言があるが、亥の月に立冬があり、子の月に冬至が、丑(うし)の月に冬の了(おわ)りが告げられ、寅(とら)の月は(旧)正月。春がやってくるのに、寒さが続く。
一日十二刻を十二支でよぶときにも、今日一日の了(おわ)りと明日の一日の一(はじめ)を意味した子の刻は真夜中で、夜の陰が深く、季節の冬至と同様、夜明け前の寅の刻まで夜陰が続く。ありていに申せば、四季の陰陽、昼夜一日の陰陽の区分を感じとり読み取るのは、平成の私たちにとって努力を要する。
(次号に続く)
「にんぎょう日本」2000年1月号掲載
投稿日: カテゴリー 【現代の名工】の話
雛人形 婚礼と雪洞 vol1
雛人形 婚礼と雪洞 vol1