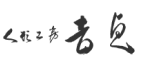初節句の男の子へ 端午の節句の由来は?

初節句 男の子へ由来のお話
端午の端は、5月に限らず月の端(はじめ)の午(うま)の日の行事でした。
やがて端午の節句は、午(うま)の月である5月の午(ご)と音が同じ五の日、
つまり5月5日に定着していきました。
この端午の節句の歴史は、古代中国における季節の変わり目の厄払いからはじまり、
日本でも奈良時代以前には5月5日に薬草を摘み、災厄をはらう風習が生まれました。
特にサトイモ科の菖蒲(しょうぶ)は剣のような葉の形と強い根の香りが邪気を祓うとされ、
さらにその「菖蒲」の音が「勝負」または武を重んじる「尚武」に通じることから、
「端午の節句」は「尚武の節句」として、武士の間で年中行事となっていきました。
江戸時代になると武家では5月5日に男の子の誕生を祝い、
武士の精神的な象徴である鎧兜や幟旗などを飾って、
その子の健やかな成長と家の繁栄を祈りました。
やがて民間でもこれをまねて大きな作り物の兜や武者人形、
紙の幟旗(のぼりばた)などを飾るようになりました。
これらの飾り物は当初、天の神様の目印となるように屋外に飾っていましたが、
江戸時代中期以降、幟旗以外は小型化したものを屋内に飾るようになりました。